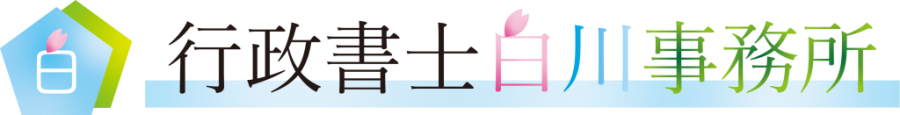ふるさと納税に関する最高裁判決について
コロナの話題からちょっと離れることができそうです。
昨日、最高裁で「ふるさと納税訴訟」の最高裁判決がありました。高額の返礼品を出し続けたことで有名な、大阪府の泉佐野市が逆転、勝訴したとのことです。
この問題は、「高価な返礼品の是非」の問題ではなく、地方自治の問題=「国と地方自治体の関係の問題」として、たいへん重要だと考えます。
そもそも、「ふるさと納税制度」自体は、「生まれ故郷など応援したい自治体に寄付すると今住んでいる居住地の住民税などが控除される」という制度で、2008年に導入されたものです。当初は、この趣旨のとおり、都会で生活しているサラリーマンなどが、財政的に厳しい生まれ故郷の自治体等を応援するものとして宣伝されました。
もともと、寄付先に関しては、「本籍」や「出身地」などのシバリがあるものではありませんので日本全国どこの市町村に対しても寄付ができる制度です。数年経ち、本来の「ふるさと」という看板から離れ、各市町村が寄付に対する返礼品を競うようになりました。それだけ、この「ふるさと納税」として、主に都会の納税者から地方に振り込まれる金額が膨れ上がり、だんだん、いびつな様相を呈してきました。
テレビなどでも、結果として差し引き2千円の負担で海産物や高級食材などの豪華な返礼品をどの自治体からゲットできるのか、という特集を組んだり、競争をあおってきたように思います。
問題になったのは、総務省はこれはいかんと思ったのでしょう。ふるさと納税で過熱する返礼品競争を抑えようと、「返礼品の金額を寄付額の3割以内に」するよう求めて総務省が自治体に「通知」を出しました。この通知は「技術的助言」と呼ばれる要請です。法的には自治体に従う義務はないのです。ここがミソです。
なぜ、「国に従う義務がない」と言い切れるのかといえば、今から20年前、1999年に成立した「地方分権一括法」に端を発します。国と自治体の関係は大きく変わっています。
それまで、自治体を国の下請け機関としてきた機関委任事務制度が廃止され、国は強制力を持って自治体を「指導」することはできなくなりました。代わりに技術的助言や勧告などの仕組みができましたが、従うかどうかは基本的に自治体の判断に委ねられることになったわけです。
そのような経緯がありながら、総務省は、昨年、2019年4月に「2018年11月以降、趣旨に反する方法で多額の寄付金を集めた自治体は除外する」と告示を行い、アマゾンギフト券を返礼品に上乗せするなどして、2018年度に全国の1割弱に当たる497億円を集めた泉佐野市など4自治体を除外するに至り、さらに、2019年6月には「返礼品は寄付額の3割以下とし、地場産品に限る」との基準が加わり、総務相が対象自治体を指定する新制度が始まった経緯があります。
「地方分権一括法」で、「地方自治体は国の下請け機関ではない」と規定されていながら、国の方針に従わない自治体は仲間に加えない、という「通知」の是非をめぐって、泉佐野市と国が争い、大坂高裁は今年1月に、泉佐野市の請求棄却の判決を行っていたものです。今回、最高裁の判決が出され、逆転して、「ふるさと納税制度の対象自治体から除外したのは違法」として、国の勝訴とした大阪高裁判決を破棄し、泉佐野市の逆転勝訴を言い渡したものです。
説明が長くなりました。
そもそも、ことの本質は、「地方自治体は国の下請け機関ではない」と定められた一括法から20年が経過し、自治体に求められる行政サービスが多様化する一方で、人口減少に苦しむ地方は人材も財源も余裕がなく、国に頼らざるを得ず、強制力のない国の助言にも従うのが当たり前になりつつあったという流れがありました。
さて、今回の判決を受けて、「本来の趣旨」に戻るでしょうか。ふるさと納税ではなく、国と地方の関係が、です。
この問題は、新型コロナウィルス対策でも、財政が潤沢な東京都や大阪府と、財政が苦しいそれ以外の都道府県のように、矛盾が見え隠れしていました。
いろいろな議論のきっかけになるものと思います。
(写真は、 はまこJAPANさんによる「写真AC」からいただきました)